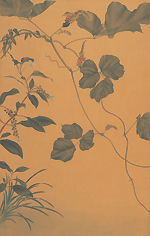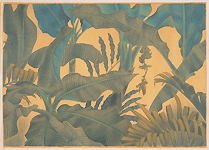私としては「日本画」でも「工筆画」でも分野はこだわらないのですが、自分の表現したい「空気」を最大限出してくれるのが「工筆画」技法なのです。
私は花鳥画(主に植物)を描くことを得意としているのでよく植物園や公園へ行き写生します。
まず描く対象をしっかりと観察(スケッチ)します。
写真だけでは描くことができません。生物学的にもおしべの数や葉の枚数までメモしておきます。写実的に、緻密に描いていきますが写真のようにそっくりそのまま描くというのとも違います。
その後、うちで構図を考えていきます。「作品」として描かれていく過程では余分なものは消化していき、時間をかけて洗練された空間を創造していきます。「間」を作ることにこそ時間をかけて何度も描きなおします。キリリと張り詰めた空気感と柔らかな時間が流れているような感じが出せるのが理想です。
写生から構図、線描、着彩までの工程で手を抜いたところはすぐにわかってしまいます。途中失敗しても修正はできないので最初から描き直さなければいけません。ですからその緊張感の中から完成した作品は達成感もひとしおです。
酒 井 幸 子 |
工筆画とは
「写意画」は作者の「意」を表現する方法で、墨や顔彩を使い簡潔な線で濃淡や強弱をつけながら描く技法です。
「工筆画」は写意画より以前の唐・宋時期に発展しました。「密画」とも呼ばれ描く対象を緻密に表現します。
中国絵画や日本画などは輪郭線を用いて対象を描写します。西洋絵画と異なる点は、描く対象を「面」でとらえて立体的に光と影とで表現するのが西洋絵画の表現方法なのに対し、東洋絵画は「線」で形を描写し光源もひとつではなく散点透視法で描かれています。
サイジング(にじみ止め)された紙や絹に鉱石や植物からできた顔料と墨を使い、薄い色を幾重にも重ね塗りして描いていきます。