| 台湾 凍頂烏龍茶的 製造体験 報告記 |
2日に渡る | |
| 凍頂烏龍茶のできるまで | ||
| をご報告します。山川幸代 | ||
| (中国茶館【悟空】立川中華街店) |
凍頂烏龍茶
台湾の南投件鹿谷郷凍頂山一帯で栽培されている烏龍茶。
堅く締まった球状の茶葉が特徴。清い香りと味、コクのバランスがよく、人気方が高い。摘む時期により香り・味に変化あり。
| 台北は桃園空港から、台中経由でバスで南投県鹿谷郷へ向かい6時間で凍頂山頂上に到着する。ここは標高740m。「凍頂」の由来は、台湾語で「ダンディン」というのが「指を踏みしめて登る」という意味で、もともとこの山は霧が多く滑りやすいためにこの名で呼ばれていたもの。後から音の近い漢字を当てたので、「凍」「頂」に意味はない(と聞いた)。 |  朝、山頂より鳳凰山側を望む |
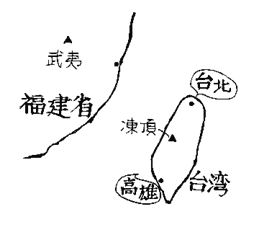 毎晩夜になると下に雲海が望め、この気候が、標高800m足らずのこの凍頂の茶を高山茶に負けない味にしているのだそうだ。不定期に霧が出、雲が降りて、環境はホントすばらしい。
毎晩夜になると下に雲海が望め、この気候が、標高800m足らずのこの凍頂の茶を高山茶に負けない味にしているのだそうだ。不定期に霧が出、雲が降りて、環境はホントすばらしい。
|
| 1 日 目 | ||
| ①採摘(さいてき) | ||
| 基本は「一芯三葉摘み」。しかし、柔らかければいい、ということで、たとえば三葉目が硬い古葉になっていれば二葉で摘んでしまうし、芽がまだ育っていなくても構わない。プロのおばさん軍団は手にカッターをつけて茎も古葉もガンガン摘んでいた。「それでいいのか」と聞くと「子どもも学校行かさないといけないしね」とのこと。重量で報酬が出るために、わりとたくさん摘んでしまうようだ。ああ現実的。 |  |
|
| ①採摘 | ||
| ②日光萎凋(にっこういちょう) | |
| 摘んだ茶葉はすぐに、広場で白い敷物の上に広げられる。 日光萎凋を行う時間は温度・湿度によって変わるため、職人さんが判断する。日光萎凋している間に霧が出てきた。日が強すぎては乾燥しすぎていけないので、このくらいの柔らかい日差しがよいらしい。20分もしないくらいで「返し」を行い、その後日光萎凋から室内萎凋に入る。 |
 |
| ②日光萎凋 洗濯物も一緒に | |
| ③室内萎凋(しつないいちょう) | |
| 茶葉を丸い竹でできた籠の上に広げ、このまま静置萎凋する。この時間も職人さんの勘で決められる。 |  |
| ③室内萎凋 | |
| ④攪拌(揺青)(かくはん・ヤオチン) | ||
| 静置された茶葉は、2時間に一度くらい攪拌を行う。手で3回、最後は竹製攪拌機を使用して、全部で4回。これだけで6時間以上かかる大仕事。手で行う攪拌は、おおざっぱにやるとおおざっぱな味の、丁寧にやると丁寧な味の烏龍茶ができる! 手首を使ってすべての茶葉を均等に揺らしていく。 4回目の攪拌で、茶葉の香りは劇的に変化を起こす。はじめは青々しいフレッシュグリーンの香りが、竹製攪拌機を回しているうちに甘さを増し、バナナのような香りになっていくのだ!ここでつくる茶の香りを決めるので、たびたび香りをかいで、「今だ!」というところで止める。その後でもう一度静置をする。最後の静置は重要だ。 |
 ④攪拌(揺青) |
|
|
茶葉を攪拌機から竹籠に厚めに盛って静かに置いておく。茶葉はこの時点で少し赤い部分ができている。これが、葉の先端が丸まり、全体的に波打つような状態になってきたら葉脈から水分がちゃんと抜けた証拠なのだ。次は発酵を止める殺青に移るので、ここで発酵を最高潮にする。 なお、ここまでの工程で茶葉にキズをつけてはいけない。キズがつくとキズの部分から発酵をしてしまい、おいしい茶にはならない。よい発酵は茶葉の縁側からだけ発酵がすすんだ状態だ。 |
||
| ⑤殺青(さっせい) | |
| お気に入りの香りになったところで、殺青。ドラム式乾燥機の中に入れ、高温で一気に殺青を行う。温度が低いと、茶葉の中心部に水分が残り、茶にしたときに濁ってしまう。乾燥させている間に時々手を入れて乾燥機中の水分量をみてみる。このとき出ている水分に苦みと渋みの成分が含まれているので、味の調節、すなわち回転と温度の調整を行い、「これでよし」となったら乾燥機から茶葉を出し、すぐさま次の揉捻に入る。 |  |
| ⑤殺青 | |
| ⑥揉捻(じゅうねん) | |
| 殺青をした後は、間髪いれず揉捻機に入れ、揉捻する。茶汁が茶葉全体をコーティングしていくので、できた茶葉は茶汁のせいで全体がベタベタしている。放っておくとそのまま固まってしまうので、すぐにほぐして次の初乾に入る。 |  |
| ⑥揉捻 | |
| ⑦初乾(しょかん) |
| 揉捻してほぐした茶葉を乾燥機に入れる。この機械から出てきたら、水分が35%前後になっていて、ようやく1日目の工程が終了。深夜までかかるので、製茶中の凍頂は夜が短い。やれやれ。 竹籠にいれて静置し、2日目に団揉・焙煎を行う。 |
| 2 日 目 | |
| ⑧加温(かおん) | |
| 2日目。まず茶葉を少し温めて柔らかくする。 | |
| ⑨団揉(だんじゅう) | |
| 帆布に包み、それを機械を使ってきつくきつくしぼりこんで茶葉のボールをつくり、できあがったボールを団揉機にかけて、圧力を加えながら転がす。 そのままの状態で固まってしまわないように、布を開いてほぐし、それを再度温め、布に包み、転がし、ほぐし……団揉の工程は⑦と⑧のこの繰り返し。 最近は全球型といえるほど丸くなった茶葉が好まれるため、20~30回もこれを行うそうだが、あまりやりすぎると茶葉が痛むので、本当は半球型のための6回くらいが適当とのこと。 この揉捻機がある工場は、近隣の茶農が茶葉を持ち込み、団揉を委託する工場だ。南投には各工程を専門にするこのような工場がいくつもある。 |
 ⑨団揉 |
| ⑩再乾(さいかん) | |
| 団揉により丸くなった茶葉は、バラバラにほぐされ、再度水分をとばすための乾燥へ。 | |
| ⑪焙火(焙煎)(ばいか・ばいせん) | |
| ⑩までの工程でできあがった荒茶(あらちゃ)の味を試飲する。この段階でこの茶のよいところと悪いところを判断し、最後の焙火によって欠点をカバーし、長所を伸ばすので、この焙煎の部分が最終的な味を決める最も重要なところだ。青くさみがあり、香りが弱い状態だったりすると、焙煎師が青くさみをとり、香りをしっかりさせる方向で火の温度や時間を調整していく。 最新式の焙煎機は業務用冷蔵庫のような外見で、微妙な温度の設定ができるもの。焙煎機の上部に小さなトンネル状の通風口があり、そこから香りをかぎ、また水分量を感じることができる。様子をみながら90℃前後で続け、最後の最後に100℃くらいに温度を上げて仕上げる。茶葉の状態を見て「完成と判断できたら完成」だ。 この焙煎をしているときに、部屋には白いほこりのようなものがふわふわ飛んでいる。それは、サポニンとタンニンの結晶で、なめてみると苦いですヨ。 |
 ⑪焙火(焙煎) 最新式の焙煎機 |
| ⑫完成(パッキング) | |
| 完成した茶葉は水分が3%以下になっている。袋に詰めてパッキング(真空パック)。だいたい1袋は1斤(台湾の1斤は600g)で、その下は半斤と4両。 |
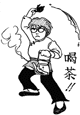 |
| 室内萎凋、攪拌中の香りは本当にさわやかで、すばらしい!私にはできあがった茶の香りよりもよいような気がしました。萎凋の段階の香り、あれをとっておく方法はないものかと思いましたが、さて? 思ったよりも焙煎の部分で味の変わりが大きく、焙煎する人の腕の善し悪しですべてが決まるような気がします。 とても疑問に思ったことを聞いてみました。「茶をつくる人はどうして一人残らずタバコを吸っているのか!?」答えは「つまらないから」「他にやることないから」だそうです。ウソか本当か、「もうビンロウをかんで、タバコを吸ってからじゃないと、いつもの味がわからないから」と言う人もいました。 百聞は一見にしかず。みなさんも中国茶の産地に一度出かけて見ませんか?中国茶がよりおいしくなることでしょう。 (やまかわ ゆきよ) |